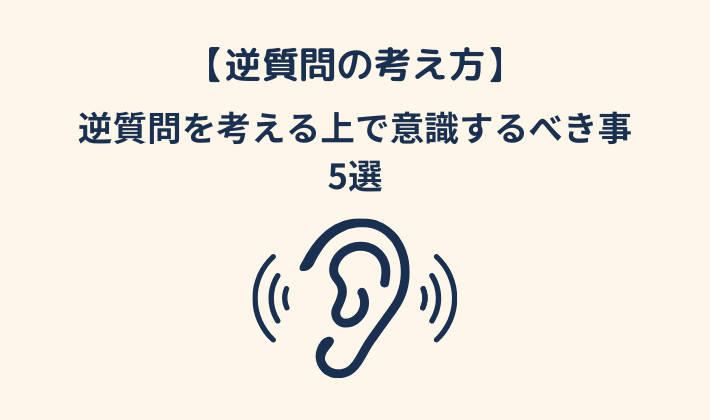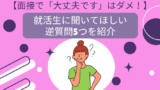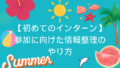こんにちは、はたてです!
面接では逆質問の時間を設けられる事がありますよね。
予め逆質問の内容を考えているとは思いますが、皆さんはどのように質問内容を考えていますか?
就活サイトでお勧めされている質問を、とりあえずそのまま聞いたりしていないですよね?
逆質問は内定を獲得する為に必要な情報が得られる重要なイベントですから、ちゃんと質問内容を考えなければならないですよ。
とはいえ、どのように逆質問の内容を考えれば良いのか分からない方も多いと思います。
なので今回は逆質問の考え方について私の意見をまとめました。
逆質問を考える上で意識すべき事を5つ紹介しますので、これから逆質問の内容を考える予定の方は是非参考にしてください。
- 逆質問の考え方が分からない
- 逆質問を考える時に何を意識すればいいのか知りたい
逆質問とは?

逆質問の考え方について説明する前に、そもそも逆質問とは何か基本的な事項を押さえておきましょう。
面接の途中、もしくは最後に就活生から面接官に対して行う質問
面接は一般的に面接官からの質問に対して就活生が回答する会話形式で進みます。
ガクチカや自己PRなど皆さんご存じの質問から、「貴方を動物で例えると?」みたいな少し特殊な質問まで色々とありますよね。
そのような質問を通して面接官は就活生の合否を判断するのですが、一方で就活生側から面接官に対して質問出来る時間を設けられる場合があります。
その時間に就活生側から実施する質問が逆質問というわけです。
私の経験上では面接の最後に、面接官から「最後に何か質問はありますか?」と尋ねられる事が多かったですね。
なぜ逆質問の時間が設けられるのか

面接官は就活生へ一方的に質問をするだけでも合否の判断自体は可能です。
就活生の回答内容を踏まえて、ある程度の能力や自社とのマッチング度合い等がイメージ出来るでしょうからね。
ではなぜ面接官は就活生に向けて逆質問の時間を設けるのでしょうか。
私は人事担当者の経験が無いのであくまで推測の話になりますが、以下2つの理由が考えられると思います。
1. 就活生側の会社に対する入社前と入社後のギャップを減らす為
就活生が就活期間中に感じた会社のイメージと入社後の会社のイメージとのギャップを減らす為に、就活生側の疑問点等を解消する目的で逆質問の時間を設けていると考えられます。
良い意味でのギャップであれば問題ありません。
就活中に聞いていたよりも社内の雰囲気が明るかったとか、若手でも自分の意見を主張出来るとか、そのような内容であれば新社会人としても嬉しいギャップでしょう。
しかし悪い意味でのギャップが生じる場合は問題があります。
なぜなら新入社員が早期退職してしまう可能性があるからです。
「想像していた会社のイメージと違う!」と言って他社に転職してしまうかもしれません。
企業としてはこのような事態が発生するのをなるべく避けたいと思っているでしょう。
その就活生を採用する為に要した費用が無駄になってしまいますし、別途新しい就活生を採用する必要がありますからね。
なので逆質問の場を通して就活生の疑問点や聞きたい事に回答し、少しでも就活生側のギャップを減らそうとしているのだと思います。
2. 就活生の志望度の高さを確認する為
就活期間中にネット検索や就活イベントを駆使して企業の事を細かい所まで完璧に調べ尽くす事は、もしかしたら可能かもしれません。
しかし多くの場合は調べきれずに、企業に対して何かしらの疑問点を抱くようになるでしょう。
そしてそのような疑問点の量や質は就活生の企業に対する志望度の高さによって大きく変わると私は思っています。
例えば極端ではありますが、支店の所在地や事業内容など調べれば簡単に分かるような内容を質問する就活生は、志望度が低そうであると何となく予測出来ると思います。
一方でより具体的な細かい内容について質問する就活生は、志望度が高そうと予測出来るでしょう。
勿論、それだけで就活生の志望度は判断出来ませんし、企業が本当にそのような考え方をしているのかも分かりません。
ですがもし私が採用する側の立場になった場合、逆質問の内容は就活生が自社に興味を持ってくれているのか判断する指針の1つになるのではないかと思います。
逆質問はどのように活用するべきか

基本的には情報収集の為に活用するのがベストでしょう。
逆質問を通してより志望企業について理解を深める事が出来ると良いですね。
どのような情報を収集するべきなのかは人によって異なります。
志望企業や就活の進捗度、内定獲得の為の戦略等の違いによって変わりますので、一概に「この情報を収集しよう!」とは言えません。
とはいえ、自分の収集すべき情報がどのようなものなのかイメージが難しいと感じる人にとっては0から考えるのも大変でしょう。
そのような人は先ずは以下の切り口から収集すべき情報を考えてみると良いかもしれません。
- 志望企業に対して疑問に思う事
- 志望企業に対してより詳しく知りたい事
今まで皆さんが参加した説明会やインターン等の就活イベントを通して、説明を聞いても分からなかった事や、もっと具体的な話を聞きたいと思った事を逆質問で質問してみると、皆さんの今後の就活に活かせる情報が獲得出来るかもしれませんね。
逆質問を考える上で意識するべき事項

それでは今回の記事の本題である逆質問の考え方について紹介していきます。
逆質問はただ単純に就活生の皆さんが聞きたい事を面接官に聞けば良いのではないかと思うかもしれませんが、実はそうではありません。
選考の通過率を上げる為に、また皆さんが本当に聞きたいと思う情報を獲得出来るようにする為に幾つかの事項を意識した上で逆質問を行う必要がありますよ。
1. 就活サイトで紹介されている質問例は参考程度に
質問案を考える上で、WEB上に沢山ある就活サイトで紹介されている質問例を参考程度に活用するのはOKです。
しかし本記事の冒頭でも記載しましたが、その質問例を何も考えずにそのまま活用するのは止めましょう。
ちゃんと自分の中でその逆質問を行う目的を明確にした上で逆質問の内容を考えるようにしてください。
目的というのは例えば以下のような内容です。
- 企業説明会で今後の海外展開はアジア圏を中心に実施すると聞いたけど、競合他社もアジア圏に注目しているケースが多かった。各社同じような動きをしていても、その狙いについては異なるかもしれないから志望企業がアジア圏に注目している具体的な理由を知りたいな。
- 新規事業としてSNSマーケティング分野に挑戦するとHPに記載があったけど、なんでこの会社がその分野に挑戦するんだろう。今後の企業戦略に関する話が聞けそうだから新たに挑戦する理由を聞いてみようかな。
- 志望企業が展開している事業内容についてはHPで確認出来たけど、概要しか書かれていないから自分の挑戦したい仕事が出来るのか分からないな。仕事内容をより具体的に把握する為に、逆質問の場で聞いてみよう。
上記のような目的を明確にした上で、どのような逆質問を面接官に聞くのか考えるようにしましょう。
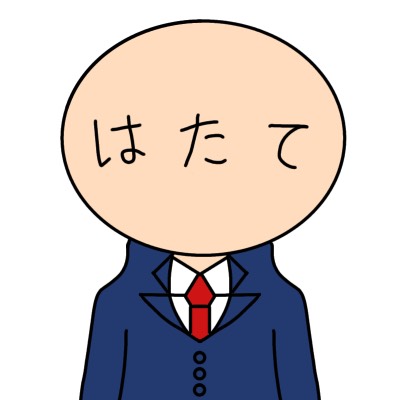
自分の目的に合う逆質問が就活サイトで紹介されているようなら、そのまま活用するのはアリですよ!
2. どの部署の人が面接官を担当するのか考慮する
逆質問では何を質問するかという観点も大切ではありますが、誰に質問するかという観点も大切です。
一般的には人事部の人が面接官になる事が多いですが、企業によっては別の部署の人が面接官になる場合もあるでしょう。
その際に例えば面接官が人事部の人であれば、ある程度の逆質問に対しては回答してくれると思います。
人事部側も就活生からの逆質問に備えて自社に関する情報を把握しているでしょうからね。
しかし特定の部署の細かい内容に関する質問や、HP等で開示されている情報以外の経営層が考えるような企業の将来戦略に関する質問等は人事部の人では回答するのが難しいかもしれません。
人事部の人も把握出来る情報に限界があるので、知らない事については明確な回答が出来ないでしょう。
人事部以外の人が面接官になる場合も同様です。
例えば面接官が営業部の人だった場合、営業に関する内容については多少細かい内容でも回答してくれるとは思いますが、商品開発部や経理部等の他の部署に関する質問は回答出来ないでしょう。
なので特に特定の部署に関する事や非常に細かい内容について逆質問をしたい場合は、次に担当となる面接官の所属部署を考慮した上で質問内容を考えるようにしましょう。
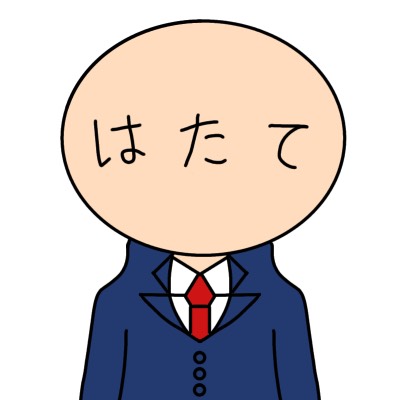
その面接官が現在所属している部署以外も過去に経験しているようであれば、当時所属していた部署に関して質問出来るかもしれません。
なので面接の中で面接官が過去にどのような部署を経験していたのか聞いてみるのも良いかもしれませんね。
用意する逆質問には人事部の人が回答出来る内容を必ず含める
先程、逆質問の内容を考える際には面接官の担当部署を考慮する必要があると説明しましたね。
ですが就活において次の面接官がどの部署に所属している人なのか予測する事は非常に困難です。
面接の際に、次の面接の担当官に関して質問しても恐らく明確な回答は得られないでしょう。
なので各段階の面接で用意する逆質問には、人事部の人が回答出来る内容を含める事を私はお勧めします。
面接では凡そ人事部の人が面接官を担当するケースが多いので、次も人事部の人が担当する事を想定したほうがリスクは少ないでしょう。
上記の内容を踏まえて反対に、逆質問を用意する上で一番避けたほうが良いのは、人事部の人が答えられない内容ばかりを用意する事です。
例えば全ての逆質問が”品質管理部に関する細かい業務内容について”であった場合、恐らく人事部の人では回答するのが難しいと思われます。
そうなるとせっかく逆質問の機会を設けてもらったにも拘らず、皆さんの望む具体的な情報が獲得出来ずに逆質問の時間が終わってしまいます。
なので次の面接に向けて逆質問を準備する際には、人事部の人でも回答出来る内容も含めるようにしましょう。
3. 面接官へ自分をアピールする事が主目的となる内容の質問はいらない
私は面接官へのアピールが主目的となるような逆質問を行う必要は無いと考えています。
理由は主に2つです。
- 逆質問の主目的は情報収集であるべき
- アピールが主目的な逆質問は寧ろアピールに繋がらない可能性あり
1つずつ解説します。
逆質問の主目的は情報収集であるべき
「逆質問はどのように活用するべきか」の箇所で記載した通り、逆質問はあくまで情報収集を主な目的として実施するべきです。
就活期間中に感じた志望企業に対する疑問点や詳しく聞きたい点について企業の人に聞くのが逆質問における効果的な活用方法だと私は思います。
他の就活生が知らないような有益な情報を得られる場合もあるので、もしかしたら一気に内定獲得迄の距離を近づける事が出来るかもしれません。
そのような可能性がある中、単なるアピールが主目的となってしまうのは勿体無いですよ。
アピールが主目的な逆質問は寧ろアピールに繋がらない可能性あり
逆質問を活用したアピールを通して本当に自分が他の就活生と比較して特徴的である事を伝えられるのであれば、逆質問の場で自分をアピールしにいくのも良いかもしれません。
しかし面接官へ自分をアピールする事が1番の目的となっている逆質問では、寧ろアピールに繋がらない可能性が高いと私は考えています。
例えばこのような内容で自分をアピールしようと思っていた方はいませんか?
- 私は○○の強みがあると認識しているのですが、貴社で働く上では他にどのようなスキルが必要でしょうか。
- 私は○○の資格を持っているのですが、貴社の仕事に活かす事は出来ますか。
- 私はアルバイトでバイト先の課題を踏まえ、業務効率化に繋がる○○等の改善策を提案していました。貴社ではこのような自分の意見を若手のうちから企業に対して提案出来る機会はありますか。
「自分のアピールしたい強みや経験+志望企業に関する事項」の組み合わせで質問するパターンです。
就活系サイトで紹介されている逆質問のリストで時々このような構造の質問を見かけますね。
これは単に自分の強み等を伝えているだけで、面接官に対してアピール出来ているとは言えません。
本当にアピールするなら、その強み等を主張する為の理由や背景についてまで詳細を伝えないと面接官も納得してくれないでしょう。
このような中途半端なアピールで逆質問のチャンスを1回消費するくらいなら、変にアピールしようとせずに内定獲得に向けて必要となる情報を淡々と収集した方が良いと思いますよ。
逆質問を通して自分をアピールする事自体は悪い事ではない
先程までの内容から逆質問の時間に自分をアピールするのは良くないというイメージを強める内容を記載していましたが、アピールする事自体は悪い事ではないと思っています。
重要なのはアピールする事が主目的になっているのか、そうでないのかの違いです。
「あくまで主目的は情報収集。だけどその情報収集のやり方が副次的な効果として自分をアピールする事に繋がる。」という状態が私としてはベストだと思います。
例えば以下のような事を意識しながら逆質問の内容を考えてみてはいかがでしょうか。
- とある内容に関するより詳しく具体的な内容について逆質問をする。
- 他の就活生には無い目線から逆質問をする。
- 志望企業の色々な就活イベントへ参加した事を踏まえた上での逆質問をする。
- 逆質問に対する面接官からの回答を踏まえて何度も深掘って逆質問をする。
重ねて言いますが、逆質問の際に自分をアピールする事自体は悪い事ではありません。
あくまで情報収集が主目的である事を忘れないでくださいね。
4. 面接官の回答がYes or Noで終わるような質問が多くならないようにする
就活における逆質問は内定獲得に向けた情報収集が目的なので、なるべく多くの情報を獲得したいですよね。
なので面接官から沢山情報が貰えるような質問の仕方を意識する必要があります。
そこで注目すべき事がオープンクエスチョンとクローズドクエスチョンという2つの質問方法です。
オープンクエスチョン
回答者の回答範囲に制限を設けず、自由に回答してもらう質問
例:貴社では新規事業として外食産業への挑戦を目指していると企業説明会で伺ったのですが、なぜ今のタイミングで外食産業に注目したのでしょうか。
クローズドクエスチョン
回答者が「Yes or No」でしか回答出来ない質問
例:私は海外で働く事に興味を持っているのですが、若手のうちから海外支店で勤務する事は可能でしょうか。
相手から多くの情報を引き出したい場合は、なるべくオープンクエスチョンを聞くようにしましょう。
クローズドクエスチョンの場合でも面接官がYes or Noの回答だけで終わる事は少ないですが、オープンクエスチョンのほうが得られる情報は多くなると思います。
とはいえクローズドクエスチョンがダメという訳ではありません。
何かYes or Noで確認したい事項があれば、クローズドクエスチョンを聞いても良いでしょう。
重要なのは両タイプの質問数のバランスです。
少ない逆質問の時間を通じて沢山の情報を獲得する為に、今皆さんが用意している質問のタイプがクローズドクエスチョンに偏っていないか改めて確認してみてください。
5. 事前に用意した逆質問に優先順位をつける
逆質問の時間は短い事が多いです。多くても3つの質問が限界でしょう。
なので事前に逆質問の準備をしている中で色々と質問したい事項が出てきた場合は、当日質問する内容の優先順位を必ずつけるようにしてください。
どのように優先順位をつければ良いか分からない方は、以下に当て嵌まる質問を第1優先の質問として考えましょう。
内定獲得に向けて今自分が獲得しなければならない情報が得られる質問
自分の興味本位や好奇心等で優先順位を決めてはいけません。
就活のゴールは内定獲得なので、あくまで内定獲得に近づける質問を選びましょう。
その為には現時点で志望企業に対して自分が把握している情報を踏まえて、内定に向けて更にどのような情報を獲得しなければならないのか考える必要があります。
どのような情報が得られれば内定獲得出来るのかゴールを見据えて、逆質問で聞かなければならない質問をリストアップしていきましょう。
考えてきた質問内容を忘れない方法
逆質問を予め考えても面接当日に緊張して何を質問しようと思ったか忘れてしまう経験はありませんか?
そんな時に使えるテクニックを1つご紹介します。
まず面接前に企業説明会等で使用しているメモ用のノートに逆質問の内容を記載しましょう。
上から順番に聞きたい事を記載しておけば、どの質問からすれば良いのか分かりやすくなりますね。
そして面接当日、逆質問の時間になったら面接官の方にこのように言ってください。
メモを取りたいのでノートを使用しても良いですか?
これでOKが貰えれば、後は事前にノートに記載していた逆質問のメモを見ながら質問すればOKです。
簡単な事前準備でスムーズに逆質問が出来るので、是非真似してみてください。
まとめ
今回は逆質問を考える上で意識するべき事を5つ紹介しました。
ポイントをまとめますと以下の通りです。
- 就活サイトで紹介されている質問例は参考程度に
- どの部署の人が面接官を担当するのか考慮する
- 面接官へ自分をアピールする事が主目的となる内容の質問はいらない
- 面接官の回答がYes or Noで終わるような質問が多くならないようにする
- 事前に用意した逆質問に優先順位をつける
今回は逆質問の具体的なリストを取り上げるのではなく、意識するべき事という観点で記事をまとめました。
誰かのお勧めを真似するだけではなく、他にも色々と考えた上で質問内容を検討しなければならない事をこの記事を通して知ってほしかったからです。
是非今回の記事を参考にして頂き逆質問を上手く活用して、少しでも多くの情報を獲得していきましょう!
ですが、どうしても質問内容が思いつかないという方もいると思います。
そのような方向けに当時私が考えた逆質問をまとめた記事を作成したので、こちらも参考にしてみてください。