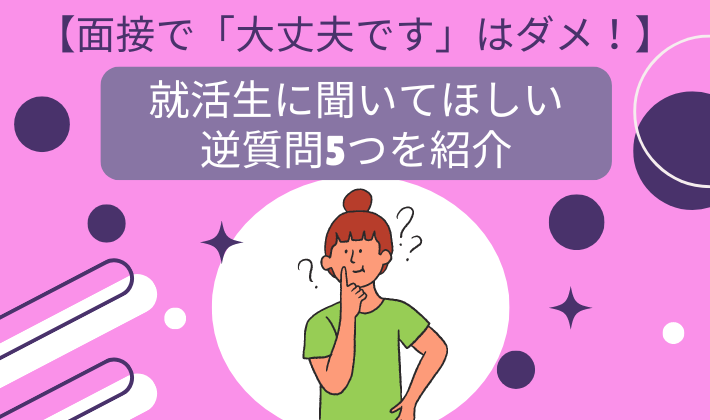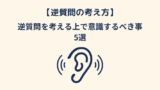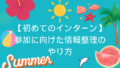こんにちは、はたてです!
「何か質問したい事はありますか?」
面接の最後に面接官からこのような言葉を言われる事があると思います。
皆さんご存知の「逆質問」というやつですね。
皆さんはこの逆質問の時間にどのような質問をしていますか?
まさかとは思いますが、「大丈夫です。」とか「特にありません。」とか言って話を終わらせていないですよね。
逆質問は聞く内容によって今後の貴方の面接や就活を有利に進める為の情報を獲得する事が出来ます。
なので最低でも1つは必ず質問する事を私は強くお勧めしますよ。
とはいっても、その逆質問の時間にどのような事を聞けばいいのか質問内容が中々思いつかないんですよね。
そのような方の為に、今回は私が就活生の皆さんに聞いてほしい逆質問を5つ紹介します。
是非、皆さんが逆質問の内容を考える際の参考にしてくださいね!
- 逆質問の内容が思いつかない人
- どのような狙いを持って逆質問をすればいいのか分からない人
なぜ面接の逆質問で「大丈夫です」と話題をすぐに終了させてはいけないのか

面接官から逆質問の時間を設けてもらった際に、質問事項が無い事から「大丈夫です。」や「特にありません。」と言ってすぐに話題を終了させる事はお勧めしません。
最低でも1つは逆質問を用意するべきでしょう。
ではなぜ、逆質問の時間をすぐに終了させてはいけないのか、その理由を紹介します。
1.逆質問の時間を有効活用しないのは勿体無いから
シンプルに逆質問の時間を有効活用しないのが非常に勿体無いからです。
確かに私も就活生当時、逆質問の内容を考えるのに苦労しました。
超本命企業であれば質問したい事も自然と浮かんでくるのですが、一方で他の多くの企業では中々質問事項が思いつかないんですよね。
私の場合、流石に面接本番で面接官から逆質問に関して聞かれた時に「大丈夫です。」と話題を終了させる事はありませんでしたが、時折事前準備を十分にせず当日の雰囲気で質問してしまう事はありました。
今思えば非常に勿体無い事をしてしまったと反省しています。
もし皆さんが面接の逆質問のタイミングで何も質問しない、もしくは目的無く雰囲気で質問してしまっているという場合は、今すぐに考えを改める事をお勧めします。
2.面接官から志望度の低い就活生と見做される可能性があるから
就活生が何も質問をしてくれない場合、面接官としては「この就活生は弊社に興味が無いのかな?」と疑問に思うかもしれません。
そうなると志望度の低い就活生として見做されてしまう可能性があるでしょう。
これは逆の立場に立って考えれば簡単に想像出来ますよね。
例えばアルバイト先で自分が学生を採用する側の立場になった時を想像してみてください。
人気のアルバイト先であればよりイメージしやすいでしょう。
面接の最後に何か質問があるか尋ねて、学生から「特にありません、大丈夫です。」と言われてしまったら皆さんはどう思いますか?
「本当にこの学生は興味を持って選考に応募してくれたのだろうか?」と少しは疑問に思ってしまうのではないかと思います。
実はその学生が凄くアルバイト先に興味を持っていたとしても、分からないですよね。
なので就活の場で先程の学生側の立場である皆さんが「逆質問は何も無い。」と言ってしまうと、面接官も就活生の志望度を疑ってしまうのです。
面接で逆質問を行うメリット

先程は面接で設けられる逆質問の時間をすぐに終了させてはいけない理由を説明しました。
ですが逆質問を考えるには結構頭を使うので、その理由を理解した上でも逆質問を考えるのは面倒くさいと思う方がいるかもしれません。
そのような方に向けて私の思う面接で逆質問を行うメリットを5つ紹介します。
1.志望企業についてより具体的に知る事が出来る
現在はインターネットが普及している事や様々な企業が就活イベントを開催している事から、自分が志望する企業に関する情報を集めやすくなっています。
皆さんも既に業界研究や企業研究を通して志望する企業に関してリサーチしていますよね。
勿論そのように情報収集をする事は就活において大切ではありますが、逆質問を活用する事によって更に詳しく志望企業に対して理解を深める事が出来るでしょう。
疑問点や理解を深めたい内容について企業の方に直接質問する事が出来ますからね。
特に面接での逆質問は就活終盤に行われる為、それまでに自分で調べた情報や参加した説明会等で得られた情報を踏まえて質問する事が出来ます。
なのである程度調査が進んだ状態から逆質問で更にその情報を深掘りする事が出来るので、より詳しく志望企業について知る事が出来るというわけです。
2.競合他社との違いをより具体的に理解出来る
内定獲得の為には志望企業と競合他社との違いを明確に理解出来ている必要があります。
でなければ、「なぜ他の企業ではなく、現在選考を受けている企業に入社したいのか」という内容を面接官に説明出来ないですからね。
業界が異なる企業同士を比較する場合はちょっとしたネット検索で各社の違いを見つける事が簡単に出来るでしょう。
しかし同じ業界に属する企業毎の違いを理解するのは結構難しいです。
ネット情報や説明会等ではその企業の大枠に関してしか教えてくれない事が多いので、競合各社の違いが分かりにくいんですよね。
一方で私を含めた社会人側は常に競合他社との差別化を意識しているので、各社においてどのような違いがあるのかイメージ出来ています。
なのでその情報をよく知る企業の方に直接質問出来る逆質問の場で、志望企業と競合他社との違いについて聞くと具体的な情報を獲得する事が出来るでしょう。
3.志望企業に対して自分の疑問を気軽に質問する事が出来る
就活の為に色々な企業について調査していると、時折疑問に思う内容が出てきます。
そのような疑問に関してネット検索で解決出来れば楽なのですが、それだけでは解決出来ない場合もありますよね。
なのでそんな時は逆質問の場で自分の疑問点に関して質問してみましょう。
企業の方に直接質問出来る機会は就活期間を通してあまり多くないので、逆質問の機会を有効活用するべきです。
4.質問内容次第で面接官に自分の志望度を伝える事が出来る
冒頭の「なぜ面接の逆質問で「大丈夫です」と話題をすぐに終了させてはいけないのか」の箇所で、その理由を自分がアルバイト先の採用側になった場合を例に出して説明しましたよね。
アルバイト希望の学生から「逆質問は特に無いです。」と言われると、本当にこの学生はアルバイト先に興味を持っているのか疑問に思ってしまう話です。
この例に関して逆に考えた場合、逆質問の場で学生がアルバイト先に関してもし色々と質問してくれたら、この学生はアルバイト先に強い興味を持っているんだと思いませんか?
それは就活にも言える事だと私は思っています。
逆質問の内容次第で面接官に志望企業に対する自分の志望度を伝える事が出来ると思っています。
事業内容に関する事、会社での働き方、直近リリースされた情報の詳細など、より具体的な内容について逆質問が出来ると、面接官側も本当に自分がその企業に入社したい事を理解してくれるかもしれません。
5.他の就活生が知らない情報を獲得出来る
内定獲得に向けて皆さんは何を意識して情報収集をしていますか?
単純に企業や業界について調べるだけでは、内定獲得というゴールを達成するのは正直難しいですよ。
なぜならあまり深く考えずに情報収集している場合、他の就活生も知っている情報しか集められない可能性があるからです。
なぜそのような情報収集では内定獲得が難しいのでしょうか。
それは他の就活生が知っている情報しか持っていないと、自分と他の就活生とを差別化出来ないからです。
内定獲得の為には自分と他の就活生とを良い意味で差別化出来るようにする必要があります。
応募してきた就活生がみんな同じような特徴しかないと、企業側も誰を採用するべきなのか決断出来ませんからね。
なので就活で実施する情報収集では基本的な業界や企業に関する情報だけでなく、差別化を目的に他の就活生が知らないような情報を獲得する必要があります。
そしてそのような情報を獲得する為に、逆質問の機会が活用出来るのです。
就活生全員に向けて開示されている企業HPやインターン等で得られた情報を踏まえて更に詳しい内容を深掘り出来れば、殆どの就活生が知らない情報を獲得出来るかもしれません。
就活生に聞いてほしい逆質問5つ

ここから就活生の皆さんに面接本番で是非聞いてほしい逆質問の内容を5つ紹介します。
勿論この5つ以外にも私は様々な逆質問を実施しましたが、特にこの5つの質問を通じて得られる情報は皆さんの就活にも活かせるのではないかと思います。
実際に私は志望動機の内容検討やキャリアプランの明確化等で自分の就活に活かす事が出来ました。
もし各質問に関する内容を読みながら「自分の就活にも活用出来る」と思える逆質問がありましたら、面接本番で真似してみてくださいね!
1.会社の将来的な戦略
具体的な事業展開や注力分野等、志望企業の将来的な戦略に関する質問です。
質問例はこんな感じです。
- 貴社の統合報告書にて今後○○分野に注力していくとの記載があったのですが、詳細について教えてください。
- 貴社を含めた業界を取り巻く昨今の市場状況では、○○の課題に対処する必要性が高まっております。貴社はこの課題に対してどの様に立ち向かっていくのでしょうか。
- 貴社では海外での事業展開も今後注力していくとの話を説明会でお伺いしましたが、具体的にどのエリアを中心に展開を計画しているのでしょうか。
この逆質問の狙いは1つです。
- 志望企業の将来的な戦略に対して自分が納得出来るか確認する為
企業の将来的な戦略は、その企業が今後も継続的に成長する為の重要な行動指針となります。
なので貴方がもし志望企業に入社した場合には、その将来的な戦略を遂行する為に仕事をする事になるでしょう。
そこで貴方がそもそも企業の設定する戦略に納得出来ないと、相当なストレスを抱えたまま仕事をすることになります。
「こんな戦略絶対に意味ないじゃん」と心の中で思いながら、会社に所属する者として戦略遂行に向けて一生懸命仕事しなければならないという複雑な環境の中過ごさなければなりません。
私なら絶対にそのような環境で仕事はしたくないですね。
完全に納得する必要はありませんので最低限、企業の戦略が的外れではないと思えれば問題無いでしょう。
まだどこからも内定を獲得出来ていない時はとにかく内定が欲しいので、多少興味があればどの企業であっても良いと思うかもしれません。
しかし出来る限りこのような入社してからの事も考えて、就活を進めていく事をお勧めします。
2.競合他社に対する差別化戦略
競合他社と差別化を図る為の戦略に関する質問です。
質問例はこんな感じです。
- 注力している事業分野について競合各社を含め同じ観点に着目しているようですが、その中でも貴社は競合他社と差別化を図る為に何か行っている事はあるのでしょうか。
- 顧客に対してニーズを捉え、解決策を提示するという各社似たような営業方針を掲げておりますが、貴社において顧客との対応で特に意識している事があれば教えてください。
- 競合他社の事業内容や経営資源等を踏まえ、貴社が特に他社と比較して差別化出来ていると感じる点があれば教えてください。また差別化出来ていると感じる観点について、どのような戦略や計画を検討しているのか教えてください。
この逆質問の狙いは1つです。
- 競合他社に対する差別化戦略を把握して、志望企業の強みを理解する為
志望企業が競合他社に対してどのような差別化戦略を行っているのかはネット情報や会社説明会等、様々な方法により情報が取得出来ますよね。
勿論そのように情報収集する行動も大切ではありますが、せっかく企業の方に質問出来る機会があるのなら、直接企業の方へその戦略について聞いてみましょう。
昨今では同じ業界に限らず、異なる業界に属する企業においても一部の事業内容が志望企業と似た内容になる場合があります。
例えば、コンビニ業界が銀行業界に挑戦するみたいな感じですね。
なので企業としては同業界だけでなく他業界の動きも意識しなければならない為、他社との差別化に向けて相当頭を働かせているはずです。
ネット情報等では確認出来ないような、より具体的な情報が企業内にあるはずなので、他の就活生が把握していない情報を獲得する為に企業の方へ差別化戦略について逆質問をしてみましょう。
そしてもしその情報が獲得出来た場合、貴方は志望企業の強みの1つを理解出来た事になります。
他社との差別化を目指した戦略なのですから、その戦略の内容は志望企業独自の動きとなるので、強みとして認識出来ますよね。
新たに志望企業の強みを知る事になるので、きっと今後の面接の回答にも役立たせる事が出来るはずですよ。
3.志望企業と競合他社との細かな違い
事業内容や社風、ビジョン等の細かな違いに関する質問です。
質問例はこんな感じです。
- 貴社とA社では共に○○事業を展開しているかと思います。調べる限り△△の点で各社の違いを見出せたのですが、その他に異なる内容はありますでしょうか。
- 将来的な企業戦略に関して各社情報開示しておりますが、大まかな内容は殆ど一緒のように思えました。この戦略について貴社は競合他社とどのような違いがあるのか具体的な内容を教えて下さい。
- 「お客様を大切にする」という企業理念については多くの企業が理念として設定しております。その中でも貴社はこの理念に対してどのような解釈をしているのか詳細を教えてください。
この逆質問の狙いは1つです。
- 志望企業と競合他社との違いを明確に理解する為
こちらの逆質問は文字通りの狙いを持って質問をするので、皆さんもイメージしやすいと思います。
競合他社との違いを理解する為に様々な媒体から情報を集めていると思いますが、調べるにも限界がありますよね。
ある程度具体的に調べられたとしても、細かい点で違いが理解出来ない場合があるかもしれません。
調べても理解出来ない内容があれば、逆質問で企業の方に聞いてみてください。
競合他社との違いから志望企業の拘りを知った
私は競合他社と志望企業との違いに関する情報を通じて、志望企業の拘りを知る事が出来ました。
就活生当時、企業分析をしている中でとある志望企業と競合他社で営業方針について明確な違いがあると思った事から、志望企業に対してその違いが生じている理由について質問しました。
すると志望企業がどのような拘りを持って今の営業方針を掲げているのか知る事が出来ましたね。
またその拘りは言い換えれば企業の強みとして捉えられるので、この逆質問を通じて新たな企業の強みを学ぶ事が出来ました。
4.仕事内容の詳細
細かい仕事内容に関する質問です。
質問例はこんな感じです。
- 貴社の営業活動では新規顧客に対して営業を行う事が多いのでしょうか。それとも既存顧客に対して営業を行う事が多いのでしょうか。
- ○○というサービスについて採用HPに記載があったのですが、具体的にどのようなサービス内容を展開しているのでしょうか。
- 貴社はグループ会社を幾つか抱えておりますが、貴社の営業活動では自社サービスに加えてグループ会社のサービスも顧客へ提案するのでしょうか。
この逆質問の狙いは2つです。
- 自分が働く場合のイメージを明確にする為
- 企業理解をより正確に行う為
1つずつ説明していきます。
自分が働く場合のイメージを明確にする為
自分が入社した時に実際にどのような仕事を行うのか働くイメージを明確にする事で、入社前後のギャップが少なくなります。
企業の採用HP内で仕事内容の詳細について紹介されている事はありますが、その情報だけで仕事のイメージを確定させるのは危険です。
実際の仕事はその情報以上に細かい内容が沢山ありますからね。
なので会社説明会やネット情報を通して、仕事内容について疑問点があれば逆質問で聞いてみましょう。
企業理解をより正確に行う為
面接で直接的に志望企業の理解度について面接官から質問を受ける事は少ないですが、それでも事業内容やサービス内容については出来る限り正確に把握する必要があります。
会社に入社したら実際に自分がその仕事を請け負う事になるので、予め志望企業の仕事内容を明確に把握していないと、いざ働く時に大変ですよね。
また面接対策的な話で言えば、キャリアプランを考える際にも正確な企業理解が必要になります。
志望企業でどのような仕事を行うのか、その仕事によってどのようなスキルや経験を得られるのか理解していないと、的外れなキャリアプランになってしまいます。
まだ働いていない就活生が仕事内容に関して質問するにしても、質問内容がイメージしにくいかもしれません。
それでも上記の質問例を参考に細かい事でもいいので、何か疑問点があれば積極的に質問してみましょう。
5.物事に対する背景・理由
将来的な企業戦略や今後の注力分野、現在の企業方針等の背景や理由に関する質問です。
質問例はこんな感じです。
- 貴社の中期経営計画では将来的な戦略として○○を掲げておりますが、なぜこのような戦略を掲げているのでしょうか。
- インターンにて貴社は今後○○事業に注力していくとの話を伺いました。貴社では様々な事業を展開している中、なぜこの事業への注力を選択したのでしょうか。
- 統合報告書より今後の事業拡大に向けて生産力強化の観点から、〇〇県に新しい工場を設立する予定との記載がありました。〇〇県に注目したのはどのような理由があるのでしょうか。
この逆質問の狙いは2つです。
- 志望企業と競合他社の違いを理解する為
- 会社の方針をより詳しく理解する為
1つずつ説明していきます。
志望企業と競合他社の違いを理解する為
物事に対する理由や背景を知る事で、競合他社との違いを理解出来る可能性があります。
例えば将来的な企業戦略について内容自体は競合他社と殆ど同じであっても、「なぜその戦略を掲げているのか」という理由に関しては異なる場合があります。
将来的に同じ目線を持っていたとしても、背景にある想いは企業毎に異なる可能性がありますからね。
そのような背景や理由から企業毎の違いを理解して、自分の就活に活かしていきましょう。
「なぜ私は志望企業でなければならないのか」等の志望動機系の質問にも回答しやすくなると思いますよ。
会社の方針をより詳しく理解する為
こちらの狙いは今回の逆質問に限らず、情報収集を行う上で皆さん意識している事項だと思います。
「なぜ○○という営業方針を掲げているのか」、「なぜ○○のような事業運営を行っているのか」など、理由や背景について知る事で、内容をより具体的に理解する事が出来ますよね。
志望企業に関する就活を進めていく上で、色々と疑問点が出てくると思います。
細かい内容でもいいので気になった事があれば、企業の方に質問してみてください。
このような質問から得られる回答は企業説明会やHPに掲載されていない可能性が高いので、質問しなければ獲得出来ない情報になります。
企業側の狙いや根幹にある想い等を知る事が出来るでしょう。
多くの就活生が獲得出来るような情報ではありませんので、その情報を上手く活用出来れば他の就活生との差別化にも繋げる事が出来ると思いますよ。
言葉の奥にある企業方針の背景を知る事が出来た
私はとある企業の説明会で、他の企業には無い特徴的な部署配属方針を掲げている事を聞き、そのような方針を掲げている背景について逆質問をしました。
すると、なぜそのような方針にしているのかという一般的には公表されていない理由に関して聞く事が出来ましたね。
他の就活生が知らない情報であり、且つ自分のキャリアプランを考える上で参考になる情報が獲得出来たので、この逆質問を通して他の就活生よりも1歩リード出来たと思います。
自分の意見も用意する事
「なぜ?」という理由や背景に関して質問する場合は、必ず自分の意見も用意しておく事をお勧めします。
なぜなら社会人においては、自分の意見を持って行動する意識が大切になるからです。
本当に自分では解決策や正解が分からない場合は、他の人に教えてもらうのも悪い事ではありません。
しかし何でもかんでも他の人に教えてもらっては、自分の存在価値が無くなってしまいます。
例えば顧客のある課題を解決させる必要がある場合、単純に上司に解決策を教えてもらうだけでは、その人は上司の意見に従って行動するだけの価値しかないですよね。
それではロボットと変わりがありません。
「自分ならどうするか」という意見を持ちながら、上司と解決策を相談出来る人の方が会社としては存在価値の高い人と認識されるでしょう。
このような話をしながらも、実は私が「なぜ?」という質問をした時には面接官から「貴方はどう思うの?」と自分の意見を聞かれる事はありませんでした。
なのでもしかしたら他の企業でも面接で自分の意見を聞かれる事は少ないのかもしれません。
私も就活生当時は自分の意見を明確に持てていたわけではないので、ある意味助かりましたが…
しかし社会人として自分の意見を持つ事は大前提の部類なので、もし面接官から自分の意見について問われた際にちゃんと回答出来れば、高い評価を得られると思います。
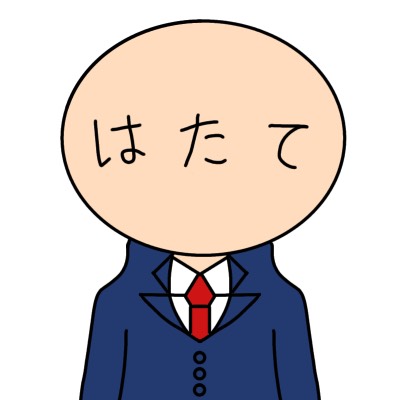
あまりにも想定していた自分の意見と企業側の回答が異なるようであれば、なぜ自分の意見とは異なるのか聞くのもいいですよ。
「私は〇〇が理由だと思っていたのですが、なぜそのような理由ではないのでしょうか」みたいな感じです。
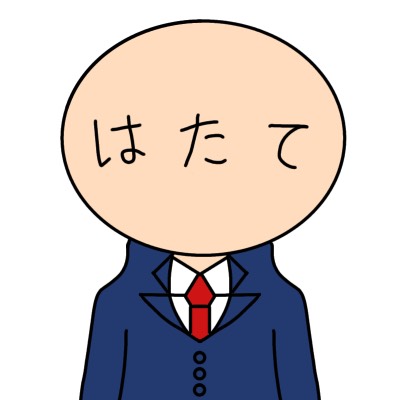
ちゃんと自分の意見を持っている事がアピール出来るので、面接官からの評価を得られると思います。
逆質問を考える上で意識するべき事

逆質問はただ単純に質問すれば良いという訳ではありません。
当日の面接官はどの部署に所属しているのか、限られた時間の中でどの内容から優先して質問しなければならないのか等、様々な事を意識した上で質問内容を検討する必要があります。
例えば志望企業の環境対策について詳細を知る為に質問する際に、面接官が環境分野とは全然関係ない部署に所属していたら、質問しても具体的な情報を教えてもらえないですよね。
このように誰に対して質問するのかという意識が大切になります。
その他、逆質問を考える上で意識しなければならない事項については以下の記事にまとめていますので、是非参考にしてください。
逆質問がどうしても思いつかない場合はどうする?

逆質問は企業の方に直接質問出来るという非常に貴重な機会なので、この機会はなるべく無駄にしたくありません。
ですが企業によってはどうしても逆質問が思いつかないなんて事もありますよね。
そのような場合は以下の行動を試してみてください。
1.内定獲得の為に現時点でどのような情報が足りていないのか考える
皆さんは興味のある企業で内定を獲得する為にどのような情報を集める必要があるのか考えた事はありますか?
皆さんが今1番志望度の高い企業でイメージしてみてください。
情報収集自体は説明会等の多くの就活イベントを通して実施しているとは思います。
就活において基本的な行動であり、非常に大切な行動ですね。
しかし先程の逆質問を行うメリットの5つ目で説明したように、何も考えずただ闇雲に情報を集め続けるだけでは、内定獲得は難しいでしょう。
なぜなら、他の就活生と自分とを差別化する必要があるという事に加えてもう1つ理由があるからです。
それは内定獲得に近づける情報を優先的に集めないと、内定までの道のりが遠回りになってしまうからです。
就活を通して集められる情報には内定獲得に近づける情報と、内定獲得とは関係の薄い情報があります。
なので何も考えずに情報収集をしていると内定獲得の為には不必要な情報の収集にも注力してしまい、最短距離で内定獲得というゴールに向かえないのです。
最悪の場合では就活期間中にゴール出来ず、内定ゼロで就活を終えてしまう事態も考えられるでしょう。
では、内定獲得に近づける情報とはどのような情報なのでしょうか。
私は以下のような情報が当て嵌まると思います。
自分が志望企業に入社したいという思いを面接官に納得してもらう為の情報
要は面接官に「確かにその話ならウチにこそ入社するべきだよね!」と思ってもらえる為の情報です。
例えばこの種の話題で王道なのは、「なぜ他の業界ではなく、志望企業が属する業界に興味を持っているのか」という内容です。
単純にその業界に興味があるからという主張だけでは、面接官を納得させる事は難しいですよね。
その業界の仕事に関係する自身の経験を説明したり、他の業界と比較して理由を説明したりする作戦を考えるのではないでしょうか?
ではその作戦を実行する為にはどうすればいいでしょう?
例えば他の業界と比較して志望企業の業界に興味を持っている理由を説明する場合は、他の業界についての情報が最低限必要ですよね。
加えて説得力を高める為に、他業界と志望業界とで明確に異なる内容に関する情報や、過去の自分の経験と関連性のある志望業界に関する情報等を集める必要があります。
ここまで読めば単に何も考えず情報を集めるだけでは、内定獲得に近づけない事は分かりますよね。
だからこそ内定獲得の為に必要な情報が何かを考えて、その情報を優先して取りに行かないといけないのです。
この行動は逆質問の場でも出来るので、自分にとって足りていない情報は何かを考えてみてください。
2.サイトに掲載されている質問集から探す
現在は様々なWebサイトで逆質問に関する質問リストが作成されています。
なのでそのサイトを参考に質問事項を考えるのもいいでしょう。
サイトによっては20選、50選と多くの質問内容を紹介している場合があるので、効率的に質問内容を探す事が出来ますよ。
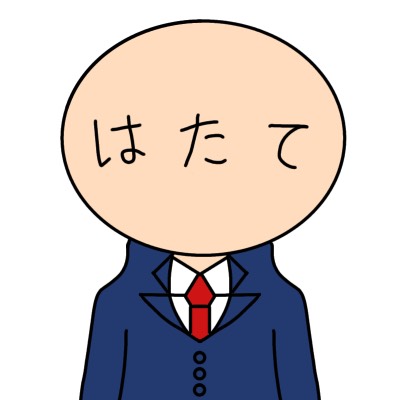
「逆質問 質問例」などで検索をかけると色々なサイトが質問内容を紹介していますよ。
紹介されている質問内容はあくまで参考程度に
Webサイトを活用すれば簡単に逆質問の内容を考える事が出来ます。
ですがその簡単さが注意しなければいけない点です。
このようなサイトを活用する上で1番やってはいけない行動は、何も考えずに紹介されている質問内容をそのまま面接本番で聞く事です。
「逆質問が全然思いつかないから、サイトで紹介されているこの質問を本番でそのまま使えばいいや」と考えていた人は、今すぐに考えを改めてください。
逆質問における本来の目的は、志望企業に対する自分の疑問点や聞きたい内容を質問する事です。
なのでその目的に沿って質問内容を考える必要があります。
他人が紹介している質問内容に対して「自分もその点について企業に質問したかったんだよね」という話であれば、そのまま本番で活用しても問題はありません。
ですが、その質問内容を通して知りたい事や解決したい事等の目的が特に無いのであれば、逆質問をする意味がありませんよ。
3.過去に情報収集した内容を改めて見直して疑問点を探す
インターンや説明会等の就活イベントに参加した際、そこで聞いた内容を皆さんメモに残しますよね?
ノートに書いてまとめたり、携帯やPCにデータとして整理したりしていると思います。
そのような当時集めた情報を改めて見直してみてください。
当時メモした時は気づかなかった事も、改めて見直す事で新たに気づける事があると思いますよ。
そこで見つけられた疑問点を逆質問で聞いてみましょう。
4.自分の逆質問に対する面接官からの回答に関して疑問に感じる点を探す
こちらは逆質問が少しだけ思いついたけど、まだ質問数が足りないと感じる方に向けた手段として有効です。
逆質問をすると面接官から質問に対する回答が得られるので、その回答に対して更に質問をしてみましょう。
多くの場合は面接官の回答に対して、その詳細を知る為に質問する事になると思います。
例えば志望企業でのキャリアに関する逆質問をした場合には、以下のような追加質問をしてみるといいでしょう。

貴社では入社してからどのようなキャリアを経験する事が多いでしょうか?
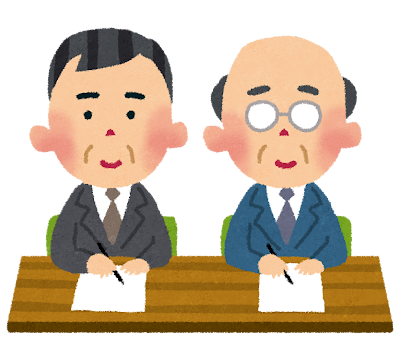
弊社では先ず、新入社員は全員営業部へ配属されます。その後、人によっては営業部として他の支店に勤務する場合もありますし、他の部署で働く場合もあります。

なぜ貴社では初期配属で営業部に所属させる方針をとっているのでしょうか?
こんな感じで詳細を聞こうとしてみると、色々な逆質問が思いつくかもしれません。
本当にどうしても逆質問が思いつかない場合はどうすればいいのか
本来聞きたい事が無ければ質問しなくても良いはずなのですが、やはり入社意欲を面接官に見せるためには最低1つでも逆質問をした方が良いと私は思います。
それでも本当に逆質問が何も思いつかない場合は、以下の質問を聞いてみると良いかもしれません。
競合他社のA社と比較して貴社が優位に立てていると思う要素はどのようなものがあるか?
この質問自体は私が就活生の時代には聞いていません。
社会人になった私が今から就活生に戻って企業に対して逆質問をするなら、という観点で考えてみました。
志望企業に対して最も競合として比べられるだろう会社を1つ取り上げて、志望企業がその競合他社よりも優れている点を確認してみましょう。
このような質問を考えた理由は、志望企業と他の企業との違いを明確に理解する為です。
就活全般を振り返ってみると、私にとってはやはり志望企業とその他の企業の違いを明確にする事が1番大変でした。
ここが明確に出来ないと志望意欲を面接官に伝えても、「その理由なら他の会社でも良くない?」って言われてしまいますからね。
最も競合として意識されている企業との違いが分かれば、絶対に志望企業へ入社しなくてはならないという自分の強い志望理由を説明しやすくなると思いますよ。
逆質問を聞く時にやってはいけないNG行動

逆質問は就活生側から自由に質問出来るからと言って、何でも自由に質問して良い訳ではありません。
逆質問を行う上で避けるべき行動が幾つかあるので紹介します。
1.調べれば分かる内容を質問する
ネットで調べれば簡単に分かるような事に関して質問するのは避けましょう。
面接官に「この就活生は弊社に関して基本的な事も調べられていないんだな」と思われてしまう可能性があります。
逆質問を通して面接官に志望意欲を示そうとするのは良いのですが、このような質問をしてしまうと逆に印象を悪くしてしまうので注意してください。
調べれば分かる内容ではなく、面接官に聞かないと分からない内容を逆質問するようにしましょう。
IR資料に注目しよう!
先程、「逆質問の場で調べれば分かる事は質問してはいけない」と説明しました。
では、どの程度まで調べれば最低限調べられたと言えるのか疑問に思う方がいると思います。
皆さんが企業研究をする際、その企業の採用HPは必ず確認していますよね。
採用HP自体も結構ボリュームが多いので、サイトの隅から隅まで全て読もうとすると結構大変だと思います。
しかし残念ながらそれだけでは最低限調べられたとは言えません。
採用HPに加えてIR資料も確認するようにしましょう。
IR資料とは端的に言うと、企業が株主やその他関係者に対して自社の経営戦略や財務状況等を開示している資料です。
具体的には以下のような資料があります。
- 有価証券報告書
- 中期経営計画書
- 統合報告書
- 決算説明資料 などなど
上場企業であればこのような資料をHP内で開示している事が多いので是非確認する事をお勧めします。
特に私が確認してほしいと思うIR資料は統合報告書と中期経営計画書です。
これらの資料を確認する事で、その企業の全体像を理解する事が出来ます。
例えば、こんな情報が理解出来るようになりますよ。
- 企業の業績、財務状況
- 過去に計画した企業戦略の結果
- 将来的な成長に向けた今後の企業戦略
- 各事業に関する具体的な取組内容
- 環境対策に向けた取組内容、現在までの取組結果 などなど
採用HPと同様に各資料かなりのボリュームではありますが、これらの資料をちゃんと確認すれば確実に他の就活生との差別化に繋がりますので、頑張って読んでみてください。
2.面接官の回答がYes、Noで終わる質問が多くなる
自分の逆質問に対して面接官の回答がYesもしくはNoで終わるような事が多くならないように気をつけてください。
勿論、YesかNoで知りたい事があるならそのような質問を聞いても良いのですが、そればっかりの質問になってしまうと面接官から得られる情報が少なくなってしまいます。
逆質問はあくまで内定獲得に向けた情報収集の場なので、なるべく沢山の情報が得られるような聞き方をするように意識しましょう。
こちらについての具体的な内容は、先ほど紹介した逆質問を考える上で意識するべき事についてまとめた記事にも記載しております。
3.オリジナルで考えた質問内容が少ない
逆質問がどうしても思いつかない方に向けて、サイトで紹介されている質問内容を参考にすると良いという話をしました。
参考にする事自体は問題無いのですが、最終的に質問内容の多くがサイトで紹介されている内容ばかりになってしまうのは良くないでしょう。
なぜならそのような質問の多くはどのような就活生でも使える一般的な内容だからです。
自分が独自で考えたというオリジナリティの要素が薄いんですよね。
企業側も逆質問がまとめられたサイトに関して認識していると思いますので、そのような質問ばかりになってしまうと、面接官は「この就活生は本当にその質問の答えを知りたいから聞いているのだろうか?」と疑問に思うかもしれません。
サイトで紹介されている内容に加えて、なるべくオリジナルで考えた内容についても聞けたほうが、面接官に対して自分が志望企業に興味を持っている事を示す事が出来ると思います。
4.面接官の回答に対して深掘りをしない
自分の逆質問に対する面接官からの1度目の回答だけで自分の知りたい事が全て聞けたのであれば、もうそれ以上その話題に関して質問する必要が無いと思うかもしれません。
通常の日常会話であればその対応で良いでしょう。
しかし就活の場であれば、私は面接官との会話を1往復だけで終わらせない方が良いと考えます。
出来ればその面接官の回答に対して、更に疑問に思った点や詳しい内容について深掘りしてほしいですね。
なぜならそのように深掘りする姿勢を示した方が、面接官に対して自分が志望企業に強い興味を持っている事をアピール出来ると思うからです。
皆さんが逆に質問される立場に立った事を想定してみると、私が面接官との会話を1往復で終わらせてほしくない理由がイメージ出来ると思います。
例えば皆さんが社会人になった後、大学の後輩から皆さんが勤務している会社について聞きたい事があると言われたとしましょう。
その際に、後輩からの質問に対して皆さんが回答をして、後輩が更にその回答を踏まえて色々と質問をしてくれたら皆さんはどう思いますか?
「この子はかなり自分が勤務している会社に興味を持っているんだな」と思いませんか?
私は上記のような感情の動きが逆質問の場で面接官にも生じると考えています。
なので出来る限り、自分の逆質問に対して面接官が回答してくれたら、そこで話題を終わらせず話を広げるように意識してみてください。
5.目的の無い質問をする
逆質問をしなければならないという思いから、ただの時間稼ぎの為に目的の無い質問をするのは避けましょう。
その逆質問を通して特に知りたい事が無かったり、特定の目的が無い中で逆質問をしたりするのは、就活生にも面接官にも意味の無い時間になってしまいます。
特に面接官に時間稼ぎで質問をしていると悟られた場合は最悪です。
それなら逆質問をしない方がまだ良い印象を残せるでしょう。
逆質問をする時は必ず自分の中で、なぜその逆質問をするのかという目的を明確に持つようにしてください。
まとめ
今回は私が就活生の皆さんに聞いてほしい逆質問を5つ紹介しました。
改めて紹介した5つの質問をまとめます。
- 会社の将来的な戦略
- 競合他社に対する差別化戦略
- 志望企業と競合他社との細かな違い
- 仕事内容の詳細
- 物事に対する背景・理由
今回紹介した逆質問は皆さんの面接本番でも聞いてメリットのある質問だと思っています。
しかし狙う業界の違いや就活の進捗度の関係から、就活生全員に適しているとは断言出来ません。
あくまで「自分は何の為に逆質問をして情報収集するのか」という目的を考えた上で、質問内容を検討していきましょう!